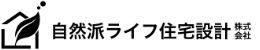お問い合わせ
家づくりに関するお問い合わせ、
設計や資金計画についてのご相談は、
何でもお気軽にお寄せください。
既存不適格建築物とは?
既存不適格建築物とは
ここでは、既存不適格建築物の基本的な意味と背景、そして現行の建築基準法との関係性について解説します。
築年数が経過した木造住宅にお住まいの方や、これからリノベーションを検討している方は、「自分の家が既存不適格に該当するのではないか?」と不安に思われるケースもあることでしょう。
この章を読むことで、既存不適格建築物の定義や扱われ方、そしてそれが実際のリフォーム計画にどのような影響を与えうるのかを大まかに把握できます。
既存不適格建築物の基本的な背景
「既存不適格建築物」という言葉を耳にしたとき、多くの方は「違法な増改築をした建物では?」とか「法律に反して建てられた危険な家なのでは?」といったイメージを抱くかもしれません。
しかし実際のところ、既存不適格建築物は“建てられた当時は適法だった”ものの“その後の法改正や基準変更によって、現在の基準を満たさなくなっている”状態を指します。
では、なぜこうした建物が生まれるのでしょうか。また、木造住宅のリノベーションを検討する際に、この既存不適格がどのように影響するのでしょうか。
ここでは、その背景や一般的なパターン、歴史的な視点から解説していきます。
法改正や都市計画の変化がもたらす「既存不適格」
明治以降、日本の建築や都市計画を取り巻く法律は幾度も改正を繰り返してきました。
大正時代には市街地建築物法、戦後には建築基準法が整備され、耐震基準や防火規定も時代に応じて強化されてきました。
特に、昭和56年(1981年)に大きく見直された耐震基準や、その後の平成時代における省エネ基準の導入、さらには近年の耐震補強促進など、幾度となく法律や基準が変化しています。
こうした改正が行われるたびに「現在の基準では認められない建物」が生まれる可能性が出てきます。
例えば、1960年代に建てられた木造住宅は当時の耐震基準を満たしていて合法的に建てられたとしても、現行の耐震基準から見ると構造的な安全性が不十分とみなされるケースがあります。
これが、典型的な“既存不適格”です。建築基準法上は「建設当時は適法だった」ので違法建築ではありませんが、今の基準から見ると満たしていない部分があるため“既存不適格”として扱われるわけです。
既存不適格=違法ではない
ここで押さえていただきたいのは、既存不適格建築物は「違法な建物」ではないという点です。
建物が竣工した時点では法に適合していたにもかかわらず、後になって基準が引き上げられたり、防火地域の範囲が拡大したり、あるいは道路斜線制限や用途地域の変更などが行われたりして、結果として「今のルールを満たさない」状態になっているだけです。
とはいえ、構造的な安全性や防火性能など、現行ルールとのズレを放置するのは建物の寿命や居住者の安全に影響する可能性があります。
例えば、旧耐震基準で建てられた住宅は大きな地震の揺れに対して脆弱なケースが多いことが、これまでの震災の記録から明らかになっています。
そのため、既存不適格であるか否かをリノベーションの初期段階で把握することは非常に重要です。
特に木造リフォームを数多く手掛けてきた弊社では、この点をまずしっかりと確認することで、後々の設計変更やコスト増を防ぎ、お客様が安心して住み続けられるプランを提案するよう心がけています。
2025年法改正で高まる関心
2025年の法改正では、いわゆる4号特例が縮小されるほか、耐震や省エネに関する要件が一段と見直されるました。
これに伴い、もともと既存不適格に当たる建物のリフォームを行う際、より厳格な審査や確認申請が求められる可能性があります。
たとえば、これまでなら大規模修繕に該当しないとされていた工事内容が、法改正以降は「安全性確保のため確認が必要」と扱われるようになったり、自治体独自の条例などで補助金を受けるために現行基準をクリアする改修が必須とされたりすることになります。
そのためには「自分の家が既存不適格なのか」「どの程度現行基準との乖離があるのか」を把握し、改修計画を立てておくことが得策といえるでしょう。
既存不適格建築物を知る重要性と確認のポイント
ここでは、なぜリノベーションを考えるうえで既存不適格の有無を早期に把握することが重要なのか、その理由を詳しく掘り下げます。
さらに、実際の現場ではどのような手順で「既存不適格かどうか」を調査・確認していくのか、具体的なポイントを示します。
築年数の経過した木造戸建てを性能向上リノベーションする際、最初に行うべきことが「図面や法的手続きの履歴確認」や「現地調査」にあるのはなぜか――ここを理解しておくことで、皆さまが今後リフォーム計画を進める際に役立つはずです。
早期把握がリノベーション成功のカギ
「建物が既存不適格かもしれない」と分かったとき、どう対応すればいいのでしょうか。
多くの場合、既存不適格だからといって即座に住めなくなるわけではありません。
一方で、リノベーションに踏み切る前にその事実を知っているか否かで、計画の進め方や必要となる費用、そして工期が大きく左右されることがあります。
例えば、外壁を張り替えて断熱性能を上げようとしたら、耐力壁の基準や防火規制が現行法に適合しておらず、全面的な補強工事が必要となるケースがあります。
また、増築や減築を伴うリフォームを計画する場合、既存不適格部分があると、その部分を含めて“新築同等の基準”で見直すよう求められる可能性もあります。
こうした事態に着手後に気づくと、追加費用や設計変更が大幅に増えるだけでなく、せっかくのリノベーション計画に遅れや混乱をきたしてしまいます。
だからこそ、最初の段階で「既存不適格であるかどうか」を調べることが重要です。
それには、法的な履歴や建築確認の状況をリサーチし、必要に応じて専門家の意見を仰ぐのが賢明です。
具体的な確認方法
では、実際にどうやって既存不適格か否かを確認するのでしょうか。
以下に代表的なステップを示します。
建築確認申請書や完了検査済証の有無をチェック
建物を建築した当時の確認申請書や検査済証が残っていれば、それが“建設当時は適法だった”証拠となります。そこから現在の法令と照合することで、どの点が不適格に当たるのかを整理できます。
図面と現地実測の突合
古い建物では、当初の設計図と実際の施工が食い違っていることが珍しくありません。
増築・改築を繰り返すうちに構造に変更が加えられていたり、隣地境界や道路斜線制限に抵触するような形状になっている可能性もあります。
図面と実測を丁寧に突き合わせることで、不整合を洗い出します。
自治体の法規制・都市計画の履歴を調べる
建物が建った後に用途地域の変更や防火地域の拡大があったかどうか、道路幅員の指定が変わったかなどを自治体の窓口や資料で確認します。
これによって、現在の基準に照らすと不適格となる部分を把握できます。
専門家による耐震・防火診断
特に木造住宅の場合、耐震診断を行うことで現行耐震基準との差が明らかになります。
省エネ診断や劣化調査などを合わせて行えば、防火性能や断熱性能が現行規準より下回っている箇所も見極めやすくなります。
上記の作業は時間とコストがかかるかもしれませんが、事前調査を怠るとリノベーション中に想定外の問題が浮上して“慌てて対処せざるを得ない”状況に陥りやすくなります。
安心して工事を進めるためにも、あらかじめ専門家のサポートを受けつつ丁寧に調べることが大切です。
違法増築との区別
なお、既存不適格と「違法増築」はまったくの別物です。
違法増築とは、当初の建築確認と異なる使い方や規模で増改築を行い、現在も違法状態が継続している建物を指します。
一方、既存不適格はあくまで“昔は合法だったが今の基準を満たさない”状態であって、法的に即アウトではありません。
ただし、既存不適格の建物に違法増築部分が付随している場合もあり、さらに複雑な問題へと発展することがあります。
その場合は違法部分の除却や是正措置を行わなければ、リノベーション全体が進めにくくなる場合もあります。
後で、違法増築パターンについても触れますので、合わせてご確認いただければと思います。
2025年法改正と事前準備のすすめ
2025年法改正によって、確認申請や構造安全性に関する運用が厳しくなることになりました。
特に既存不適格建築物のリノベーションは、専門家の見立て次第で「大規模修繕や模様替え」とみなされる工事が増え、確認申請や追加補強が避けられなくなる可能性もあるでしょう。
しかし、早めに現状を把握し、適切な計画を立てれば、補助金や助成制度を活用しながら安全・快適な住まいに生まれ変わらせることも十分に可能です。
弊社としても、既存不適格建築物の改修を数多く手掛ける中で「調べれば調べるほど事前対策がやりやすい」という実感を得ています。
皆さまも、リフォームを計画する際にはぜひ“既存不適格かどうか”を早めに確認し、長期的な視野でライフプランと照らし合わせた最良の選択をしていただきたいと思います。